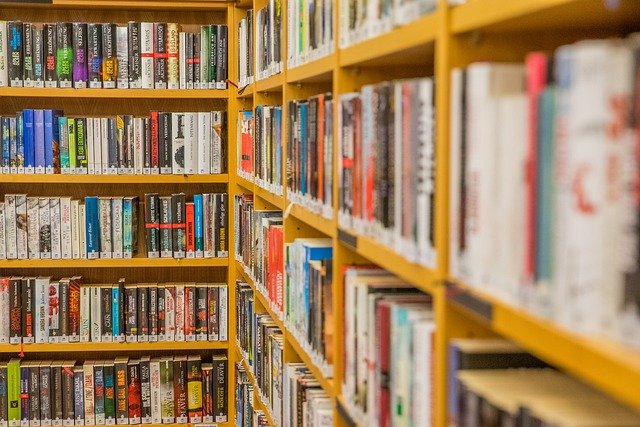すぐ読める目次
『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる! 』要約・書評・レビュー
本の基礎情報
| タイトル | 『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!』 |
|---|---|
| 出版社 | すばる社 |
| 発行 | 2014年 |
| 著者 | 松永 暢史(まつなが のぶふみ)
|
著者は、国語指導、特に「音読」を中心に数々の子どもたちの能力を開発されてきました。
他には、男女の育て方の違いに目を向けた本が有名ですね。
本の要点・書評
『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!』の要点
- 「本」こそ最高の知育教材
- 読書量で子どもの学力が決まる
- 読み聞かせで地頭の良い子が育つ
【要点1】「本」こそ最高の知育教材
子どもが幼いうちは、のびのびと育てよう。
周りの子どもと自分の子どもを比較して、早くから英語学習や勉強をさせる必要はない。
「本を読む習慣」をつけるだけで、後伸びする地頭の土台をつくることができる。
特に、読み聞かせをたっぷり行うことで、自ら学ぶ子どもに育つ。
【要点2】読書量で子どもの学力が決まる
「本をよく読む」=「勉強ができる」
特に、幼児期からのたっぷりの読み着かせで、「日本語了解能力」(国語力)がつく。
読み聞かせは、子どもの「読書量の貯金」となり、小学校高学年~中学校頃から後伸びする学力の底力となる。
読み聞かせや読書習慣から、子どもの興味分野が開花する。
興味や好奇心は、自ら学ぶ力に直結する。
よって、学力向上につながる。
- 思考力
- 集中力
- 表現力
- 文章理解力
- 語彙(ごい)力
【要点3】読み聞かせで地頭の良い子が育つ
読み聞かせの目的は、日本語の「音を聞かせる」こと。
絵本に書かれている一字一字のすべてを、子どもの耳から体内へ注入させるようなイメージで読んで聞かせること。これが、読み聞かせです。
同著p.47
著者の提唱する、読み聞かせの方法。
- すべての音をしっかり
- 同じ強さで発音する
「一音一音ハッキリ読み」を取り入れることで、子どもが聞き取りやすく、集中して話を聞くようになる。
結果、「日本語了解能力」(国語力)を早い段階で子どもにつけられる。
例えば、
- 文章構造が自然に理解できる
- 日本語の助詞や助動詞の働きが分かる
- 一音一音ハッキリ読む
- 声色は自然な感じで
- 文章を変えて読まない
- 年少ほど、ゆっくり読む
- 寝転がって読む
→【寝転がって読む】の真相は、本を読んでみて下さい、面白いポイントでした。
本のレビュー
【良いレビュー抜粋(Amazonより)】
この本の中で紹介されているおすすめの本もオススメです。
何冊も後日購入しましたが、大概どの本も子供の食いつきがよく、
買って良かったと思える、満足できる1冊でした。
一才の娘の読み聞かせの参考にならないかな?と思い購入してみました。
書いてある、お経の様に読む読み方には、絵本が好きな娘が逃げ出したのでやっていませんが、年齢別の本紹介はすごく参考になりました。
この本のおかげで、教育に良いと分かってはいたけど、面倒だと思っていた読み聞かせをすぐに実践することができました笑。
おすすめの本を何冊も挙げており、大変為になりました。
★読み聞かせのオススメ本が、145冊も入っているのがお得で、選ぶ手間が省けたという評価が目立ちました。
【悪いレビュー抜粋(Amazonより)】
本は最高、とりわけ音読の必要性が書かれていますが、研究成果/エビデンスはほとんど示されておらず、筆者の意見として書かれているので抵抗がある方もいらっしゃると思います。
私はちょうど小さな子供がいるので購入してみました。
子供に本は何でも買い与え、ゆっくりはっきりリズム良く読んであげることで、子供が興味を持ち、理解し読書好きになる。
それを続ければ勉強ができるようになる、とありますがそれはこれから子供の成長を見ないとわかりません(笑)
参考になり、面白かったのですが、読み聞かせのやり方には少し疑問も…。これから試行錯誤してはみますが…。
あと、おすすめの絵本ももう少しボリュームが欲しかったです!
★著者の経験に基づく話が多いため、論理性やエビデンスに欠ける点に不満があるレビューが目立ちました。
<年代別>具体的な実践+音の良いオススメ本
本のタイトルが、『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる! 』ですので、10才超えてしまったら今さら何をやってもムリなの?!
そんなわけではないようです。ほっ。
年代別に、この本から学んで実践できることを具体的にみていきましょう。
また、著者が「音の良い」オススメ本を紹介してくれていますので、リンクを貼っておきます。
具体的に何を読めば良いか分からない!という方にはヒットする情報です。
赤ちゃん
「読み聞かせ」の始め時は早くてOK。
家にある本を、今すぐ「一音一音ハッキリ読み」で始めていきましょう。
- 子どもの興味のある本
- 何度も何度も「読んで!」と言ってくる本
読み聞かせる本は何でもOKです。
以下、著者のおすすめ本のリストです。
1、2才向け「音の良い絵本」
- ストーリーは最小限に
- リズムがゴロが良い
- 短文にギュッと言葉が凝縮されたもの
(2023/05/14 02:42:37時点 Amazon調べ-詳細)
(2023/03/30 19:42:37時点 Amazon調べ-詳細)
(2022/07/22 03:32:38時点 Amazon調べ-詳細)
(2022/12/14 02:22:40時点 Amazon調べ-詳細)
(2022/11/03 20:57:17時点 Amazon調べ-詳細)
(2022/06/14 22:22:43時点 Amazon調べ-詳細)
(2022/06/14 22:22:44時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/04/26 05:52:36時点 Amazon調べ-詳細)
3、4才向け「音の良い絵本」
- シンプルなストーリー
- 小学生でも楽しめる
- 子どもの好みをよく聞いて選ぶ
(2023/05/19 03:50:55時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/04/26 10:32:39時点 Amazon調べ-詳細)
(2022/10/01 13:22:37時点 Amazon調べ-詳細)
(2023/07/28 16:42:41時点 Amazon調べ-詳細)
(2022/06/30 20:12:40時点 Amazon調べ-詳細)
(2022/10/23 17:59:43時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/04/26 07:52:38時点 Amazon調べ-詳細)
5、6才向け「音の良い絵本」
(2022/10/04 19:32:37時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/04/26 11:32:37時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/04/26 11:12:40時点 Amazon調べ-詳細)
(2022/11/20 03:32:33時点 Amazon調べ-詳細)
(2022/06/10 22:02:41時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/04/26 11:12:37時点 Amazon調べ-詳細)
(2023/09/07 07:32:45時点 Amazon調べ-詳細)
本に興味を示さないお子さんは、どうする?
本に慣れていないお子さんや、活発で体を動かすのが大好きなお子さんもいますよね。
著者によると、次のようなポイントで本に仲良くなれるチャンスがくるようです。
- ムリにあたえようとしない
- 無理強いせず、いろんな本を身近に置いておき読み聞かせできる機会」を待つ
- 歌もひとつの読み聞かせ
- 日本の童謡の美しい歌詞メロディを子どもに聞かせよう
- 「紙芝居」を利用する
「紙芝居」を使うと、”とある秘密兵器”のおかげで子どもが集中するとのこと。
なるほどな~と感心しました。